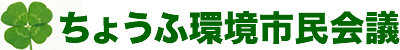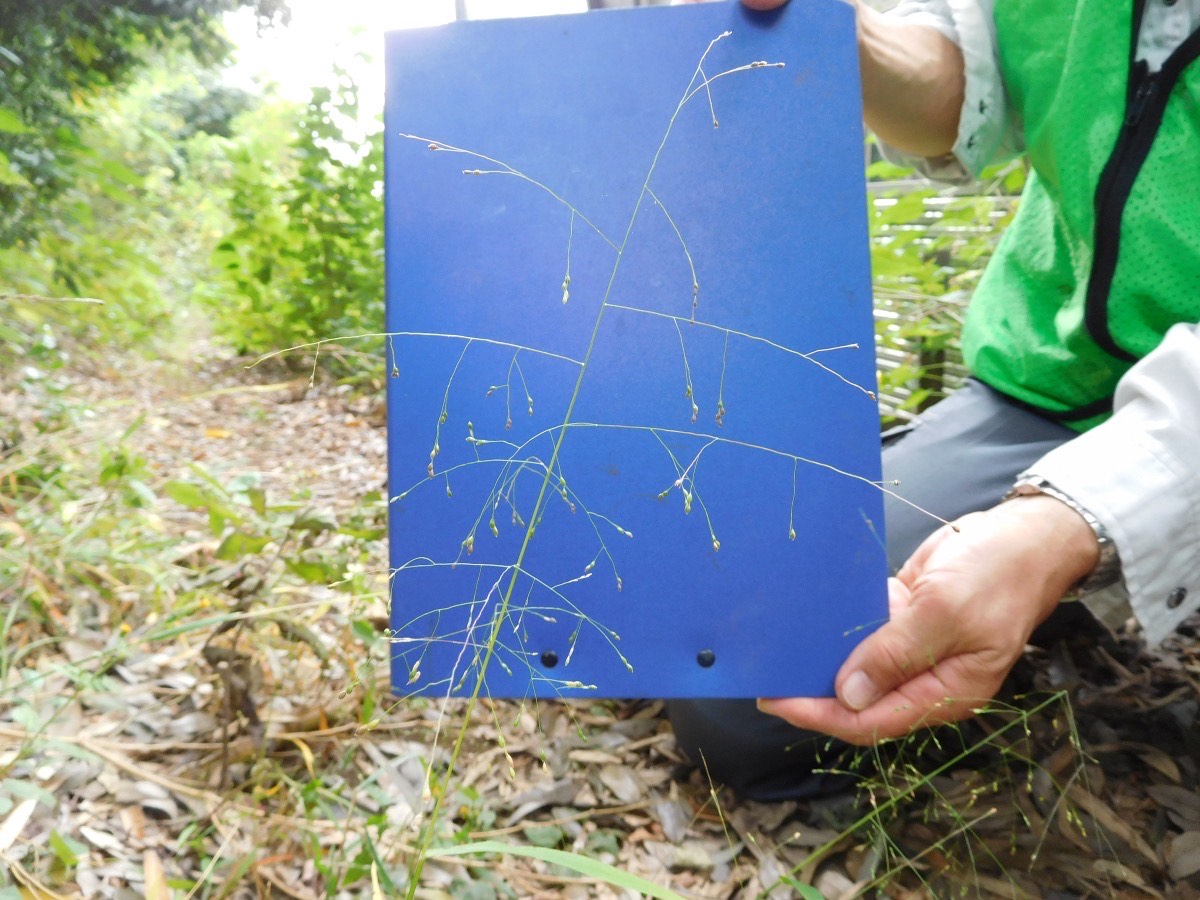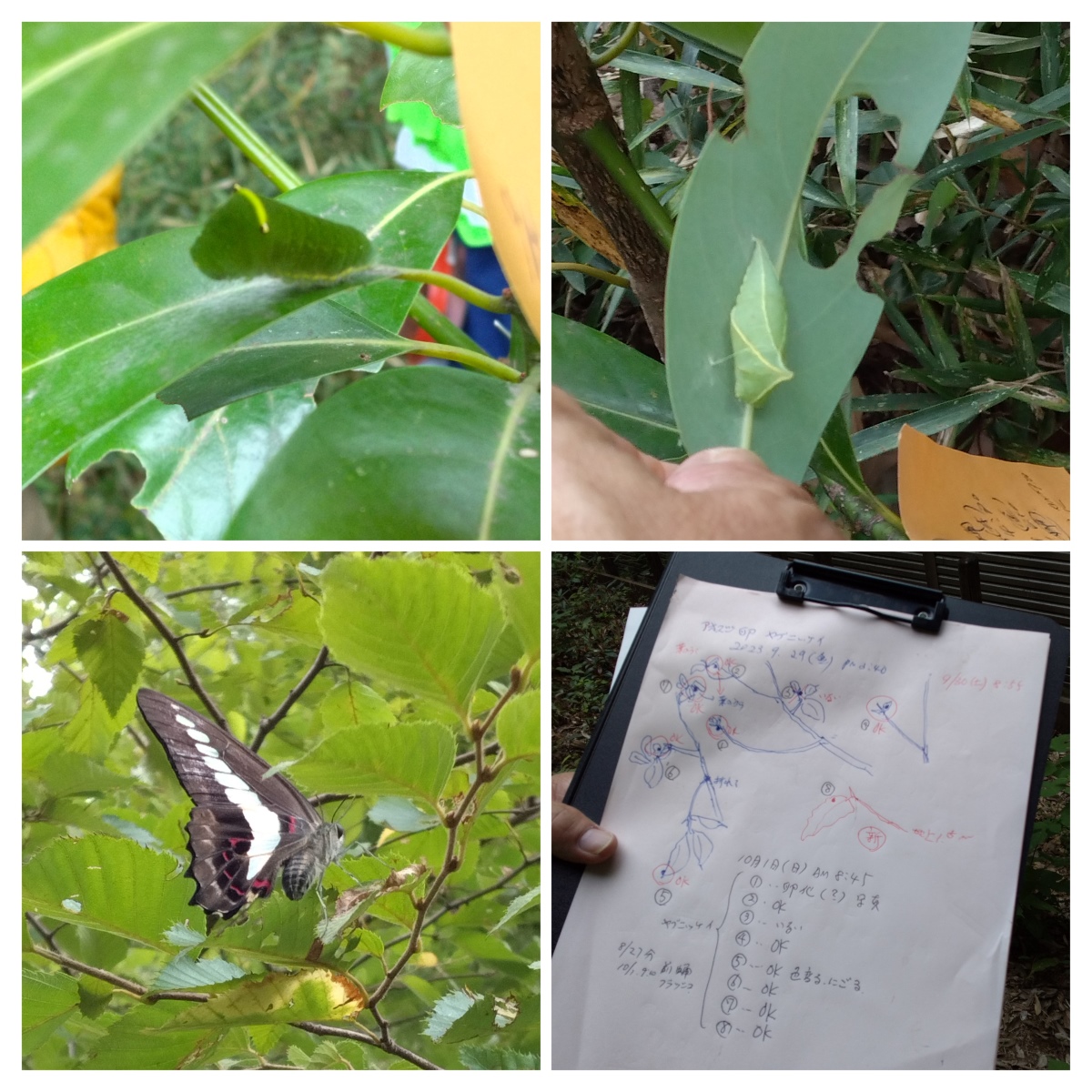カニ山の会 今年最後の草刈り
12月9日(土)晴れ 参加者13名+3名(体験参加)
今日の作業場所に向かう時にカマドの前を通りかかると消火のために水をかけられた枯れ木が残っている。先ほど見廻りの方に聞いていたことだが、誰かのいたずらか。乾燥した冬は特に危険な行為。2度と無いことを祈って。

今年最後の活動日。今日は東樹林上段のササ刈りと実生稚樹の除伐、常緑樹の剪定を全員で実施することにした。

10㎝20㎝のササだが放っておくとすぐにヤブ状態になる。女性陣は時折「これなんだろう?」とオモトやキンランを確認しつつ確実に進め、刈り取ったササは下段に作った囲いに廃棄した。
またあちこちに山積みにしていた剪定枝や落枝は通路際に粗朶垣風に積み、ある程度太い枝は廃棄用に他の場所に山積みし、きれいに片付けて東樹林内の中央はすっきりした空間になった。

斜面に粗朶垣風に枯れ枝を積む。土砂などの流れ止めにもなる。

さっぱりした東樹林前々から気になっていたヤマユリ。今日はこんな状態になっていたのを発見! 種が入っているかは確認しそこなったが花が咲いたことは確実。 東樹林内では例年ヤマユリらしき葉を確認していたが花が咲いているのは見たことが無かった。それでもこれは確かに花が咲いた証拠。来年は必ず花を見てみたい!

ヤマユリの果実
サザンカだと思いますが、すばらしく真っ白な花。
マンリョウも赤い実をたくさん付けて、もうすぐお正月。その他
11月中頃より業者によりカニ山の何ケ所かで土留め工事が行われた。野草園北側階段、ひきずり坂野草園前の崩落崖部、そして東樹林内中段の通路(今までは丸太を並べていた場所)にも土留め板が設置された。板にやや高さがあるので今後の雨水の流れなどは気になるところ。またキャンプ場横にある倉庫(テーブル・イス・食器)の貸出中止についても行政に問い合わせをした。
様々な動機やモチベーションで参加する会員と折々に話をしながら来年も今年以上に楽しくやっていきたい。年明けは根回しをした樹木の移植について場所・時期を決定し力作業をする予定。(S&K)
入間・樹林の会
2023年12月17日(日)晴れ 気温14.3℃
参加者:8人
晴れて気持ちのよい作業日だった。全員で林内巡回をして、通路の通り抜けなど検討した。作業は、駐車場へ枝がはみ出したエノキの伐倒は難しかったので、枝を切り落としてすっきりした。時期ではないがアジサイの剪定をしたので見通しがよくなった。来年花が咲くのが楽しみである。フウランの補植をして土留めにした。
これまではマンリョウが多いと思っていたが、林内にセンリョウの実が赤くなってあちこちに生えているのがわかり、思いの他センリョウがたくさん生えているのがわかった。オモト、キミセンリョウ、シロミマンリョウ、ヤブラン、ヒヨドリジョウゴ、ムラサキシキブ、ヤツデの実がなっていた。(報告:安部)

1 はみ出した枝の剪定作業
2 きれいになった坂道(清掃)
3 アジサイ剪定
4 オモトの実
5 目立つようになったセンリョウの実
6 シロミマンリョウの実
7 キミセンリョウの実
8 ムラサキシキブの実
9 サザンカの花