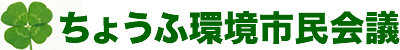「ナラ枯れは長い間虫害とされてきた。しかし近年の研究により、ナラ枯れで樹木が枯れる直接の原因は菌類であること、および、病原菌をカシナガ(カシノナガキクイムシ)が運んでいることが明らかになった。すなわち、ナラ枯れとはカシノナガキクイムシが病原菌を伝播することによって起こる、樹木の伝染病の流行なのである。」(森林総合研究所『ナラ枯れの被害をどう減らすか―里山林を守るために―』P.2)
ナラ枯れの厄介なところは、伝染病であることです。人間界のコロナ渦と同じく、放置すると感染拡大が止まらなくなります。8月末現在、若葉町の崖線樹林で被害が集中しているのは若葉町3丁目第2緑地(約3460㎡)で、この緑地の優占樹種であるコナラ45本のうち9本が感染。隣接する第1緑地と第3緑地でもシラカシ10本、第2緑地から約600m南の入間町2丁目緑地でもコナラなど7本の被害が確認されています(以上のデータは衛藤譲二さん調べ)。
なかでも第2緑地の樹木番号224と216はすでに全ての葉が赤褐色に枯れ、枯死したものと思われます。しかも、224は樹高25m、胸高直径84.3㎝というこの緑地随一の巨樹です(番号と大きさは平成26年度の調布市による毎木調査データ)。500mほど離れた地点からこの森を遠望すると、まるで紅葉のような224と思われる樹冠が頭を出しています(下の写真)。

実篤記念館付近から遠望当面の対処方針
樹木番号216も樹高24mの巨樹ですが、緑地を横断する坂道(大坂)に接して生えているため、その樹冠は大坂に被さり、さらに筋向いの住宅の頭上に達しています(下の写真)。枯死していれば、秋の台風による倒木が心配です。そこで調布市は早急に216を伐倒処理し、その材はすみやかに搬出(当初は11月まで現場に置く予定だったが、東京都の指導で変更)。根株はカシノナガキクイムシが出るのを防ぐためにビニールで包むとのこと。ただ、根株を燻蒸する必要がないのか、また燻蒸に用いる薬剤の安全性はどうか。そういった点を今後確かめたいと思います。ちなみに、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(1962年)はナラ枯れに似たニレ(楡)枯れ病対策に用いられたDDTを問題にしています。

大坂上住宅に接する崖線樹林にも感染拡大
第1緑地から六別坂(崖線を横断する坂道のひとつ)を挟んで北側の柳邸跡地では、下の写真のように住宅に接する樹木の一部が枯れています。右手の2本は最近、枝落としされた跡がありますが、枯れているのは別の木です。被害木には老齢の大木が多い傾向があるが、この木はまだ若いようです。近づけないので樹種不明ですが、要注意です。

柳邸跡地第2緑地から約300m北側の崖線樹林で下の写真のような枯れた木があります。ご近所の方に聞くと、7月から枯葉が目立つようになったと。ここも接近して調査することが難しいが、平成26年度毎木調査の15番コナラ、樹高22mと推定。この一画にはコナラ4本を含む20本があり、多くはナラ枯れの感染がありうるブナ科樹木です。住宅に被さる位置にあるので、感染防止策とともに、感染木の伐倒による倒木リスク回避が必要で、目が離せないと思います。

大野さん宅裏崖線温暖化の影響も
ナラ枯れは三鷹市の国立天文台の森や野川公園で広がり、港区白銀の国立自然教育園の森でも目撃したとの情報があります。全国的に見ると1980年代から山陰や中部地方の日本海岸で広がり、関東や東北にも感染域を拡大してきました。2010年には北限だった秋田県から青森県の森に伝染し、昨年来、1万4000本以上と過去最大の被害が出ています(2020年8月3日朝日新聞青森版)。暖冬が多くのカシノナガキクイムシの越冬を可能にしていると指摘されています。
都市林の先を見越した対策を
青森の場合は山の森林での感染発生で、カシノナガキクイムシを集めて処理する「おとり丸太法」などの対策が採られています。ただ、崖線樹林のような都市林の環境では採用できる対策が限られます。倒木リスクを考えれば、感染木の伐倒、焼却処分もやむを得ないのではないでしょうか。都市林の保全策として、老齢化・大木化したコナラなどを温存して森の更新を促さず、林床を明るくする「公園型」保全策が多く採られてきたことが、ナラ菌が感染しやすい状況をつくったとの指摘もあります。伐倒処理する樹木をバイオマス燃料として利用する事業を起ち上げ、その利益を伐倒後の樹林の再生につなげる。こういった明日につながる対策が必要ではないでしょうか。(大村)