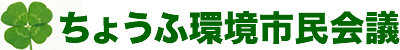若葉緑地の会 桜伐採の「あと」をどうするか
1月8日(日)晴れ 参加者4名
1月度の活動は例年休みにしているが、12月の活動日が安全講習と重なるなどして十分にできなかったので、1月8日を臨時活動日とした。緑地内外のゴミ拾いのあと、緑地内散策路と「広場」の落葉掃き。次いで崖線上段「第一広場」の半分近くに蔓延ったアズマネザサを刈った。

12月に伐採した桜の老木5本の大きな切株が「桜広場」に残された。これを「痛々しい」と感じるのは、余計な感傷だろうか。
切株(下の写真)の年輪を数えると、80本以上あった。この場所は元は民家の庭で、80何回かの陽春の訪れを地域に告げてきた桜たち。そういえば、近年では花の咲く位置が高いため、緑地の中ではあんまり花が見えず、思いがけず遠い場所で甍(いらか)の向こうに見えた桜花がここの桜と判ったこともあった。
老木5本は、樹勢が明らかに衰え、幹が斜立し、大した強風でもないのに太枝が落ちたことから、緑と公園課に伐採を提案していたもの。危険除去の点から適切な判断だったと思う。実際の伐採作業も、重機を入れた二日がかりの大仕事で、経費も半端ではなかったようだ。しかし、私たち市民ボランティアも、地域の住民も、この伐採を見守り、その後利用について考えることがなく、行政と業者任せで事を進めてしまったことに、悔いがある。一昨年以来、ナラ枯れの感染防除のために大量伐採されたコナラやシラカシの行末も、私たちは知らぬままだ。
若葉の森3・1会では、台風で倒れたコナラの玉切りした幹を残してもらい、それをベンチに加工して「富士見スポット」に置いている。街の木ものづくりネットワーク(マチモノ)という団体は、公園や緑地の伐採木を公共施設や街の家具などに加工するプロジェクトを進めてきた。実際に調布駅南口の「子育てカフェaona」(2015年開業)のテーブルや椅子に使われ、最近でも南烏山の「まちづくりカフェMuimui」の壁材になっている。こうした実績を知りながら、桜の老木伐採と結びつけることをしなかったのは、私たちの怠慢だったと思う。

桜の老大木5本の伐採によって、「桜広場」の林冠には大きなギャップができた。伐採木を引き摺って搬出したため、地面がかなり広く露出している。そこに陽が射し込んでいた。この「新天地」をどう利用すれば良いだろうか?放っておいても、この夏にはアカメガシワなどのパイオニア植物が生い茂るだろうが、やはりこの樹林の「次の世代」のメンバーたちを育てる手伝いを、私たちがやるべきだろう。住宅地で3方を囲まれていることを踏まえると、高木種は避け、中低木の苗木畑にすべきか?

あるいは、ここが元は民家の一画であったことを踏まえると、樹木にこだわらず、野菜や花、ハーブ類の畑として利用してもよいかもしれない。いや、そのほうが多くの市民が緑地に関心をもち、身近な場として出入りするのではないか。
1月28日の調布市環境団体交流会では「地域コンポスト」の興味深い提案があった。樹林が生産や暮らしの場ではなくなった現代、その持続的保全のためには、地域住民はもとより多くの市民がそこに係わることが不可欠だ。樹林から出る落葉や剪定枝に家庭の生ゴミを加えてコンポスト(堆肥)とし、地域住民や市民が樹林の一画でコンポストを使う畑づくりをする。
従来の樹林保全ボランティアも大切な役割だが、実際の参加者は限られる。もっと幅広い市民の関心に応えて、樹林で楽しみながら身体を動かし、「実利」もあるような活動の在り方を、アタマを柔らかくして、具体的に考えていきたい。
日当たりが良くなった「桜広場」の一隅で、マンリョウの実が日差しを浴びて輝いていた。
なお、このレポートの筆者・大村は1月8日の活動日直後に新型コロナの感染が判明した。当日は体調不良を自覚しながら活動に参加していた(マスクは着用)。幸い他のメンバーに感染者が出なかったものの、やはり参加を見送るべきだったと思う。(大村)

カニ山の会 新年の山開き
1月14日(土)曇/小雨 参加者17名
例年、1月の作業日には山開きと称して大木の前で1年の安全を山の神様にお願いしている。



そして欠かさず行ってきた懇親会、昨年は雪のため行えなかった。今年度春(2022/4)入会の新メンバーは、焚火と鍋を囲こむ親睦会のほっこり感を味わえるのは初めてになるので是非とも実施したかった。開始時から小雨が降り出しそうな危なっかしい空模様だったが、鍋を食べ始めた頃から葉っぱの雨音が 聞こえるほどに降り始めた。それでも全員の協力でターフ代わりのブルーシートテントが出来上がり一体感が一層高まった。

山開きを始める間際、今期の雑木林ボランティア講座生Oさんが倅くんを伴って現れ、飛び入り参加。ほとんど最後まで 一緒に歓談した。 会にも入ってくれるそうだがバリバリの現役社会人、無理は禁物、でも現役世代の中にこんな活動が広がる起点として一緒に楽しくやって行きたい。
また退会した前リーダーさんが差し入れを持って顔を出してくれた。メール連絡は続けているので「多忙な中でもカニ山の作業等に助言を寄せて欲しい」と話ができたし、声掛けをした環境活動仲間の方も顔を見せてくれて、冷たい小雨の中でも楽しい歓談の場となった。(S&K)
入間・樹林の会
2023年1月15日(日)曇り 気温12℃ 参加者8人
新年最初の活動日。初めに入口のシラカシの木に安全祈願。泡が木の根元に何か所かあり、「これは何だろう?冬なので卵ではないね」と調べると「樹幹流」木の表面の物質が雨によって流され泡になるとのこと。その後、塩・酒・米、道具を備えて今年1年の安全を祈った。
3手に分かれて、落ち葉だめ付近や坂道・通路整備、方形枠調査、懇親会準備を行い、全員で3か所の植生調査を実施した。雑木林広場 28種、シャガの広場38種、ツバキの森13種を確認した。
冬枯れや落葉でわかりにくいこともありながら以前の調査を思いだしながら行った。ツバキの森には、クスノキが新たに2本出現していたが、鳥が運んだのだろうか。落葉して、林の中は見通しがよくなっている。
エナガ・シジュウカラ・メジロがよく鳴いていた。崖線ウォークで発見し先月駆除した同じ杉をひっくり返すと再び、スズメバチ女王バチが冬眠していた。夏に襲われないように駆除した。
雨予報だったが、懇親会中は降らずにいて、今年も楽しく安全に活動しようと確認しあった。ヤブラン、センリョウ、マンリョウなどの実物を確認した。(安部)
入口のご神木のシラカシに安全祈願

泡ふき?虫?いや樹幹流です

女王スズメバチは枯れ木の中で冬眠

キミセンリョウの実

クスノキの鎌のような芽、これが特徴

懇親会 根本講師