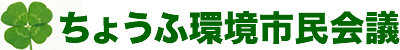若葉3・1会 カシナガトラップの手入れ
7月2日(日)晴れ 参加者9名
気温が30℃を超える日が続き、すっかり夏になった若葉の森は、日当たりもよく、イヌシデ、ケヤキ、シラカシ、孟宗竹等の枝葉がよく伸びていました。様々な雑木が生い茂り、 隣接する住宅地との境付近は見通しが悪くなってきていました。

ナラ枯れ被害防止のために、若葉の森でもカシノナガキクイムシを捕獲するための「カシナガトラップ」を設置しています。コナラやシラカシの幹に取り付けてあるトラップを一つ一つ外して、捕獲状況の確認を行いました。トラップの中に仕掛けた水をザルにあけ、 何頭捕獲できたかピンセットでカウントします。確認後は新たに水と中性洗剤を仕込んで、 再度幹に取り付けました。

第二緑地のキンラン坂下付近は、2021年12月の安全講習会にてアカメガシワなどの藪を大掛かりに伐採したので日当たりがとてもよくなり、その後はコナラの実生が多く育つようになりました。様々な雑木が生い茂ってきていたため、葉の形状を確認しながらコナラ以外の雑木を伐採しました。写真下は、伐採した植生(ツル類、ヒサカキ、シュロ、タケニ グサ、イヌシデ、ヤマハゼ、クサギ、アカメカシワ、ゴンズイ、エノキ、ケヤキ)。

六別坂下入り口に設置している浸透ますの様子です。先月(写真左)時点では、第一緑地の中央斜面から流れ落ちた泥が堆積し、浸透ますをすっかり覆い隠していました。その際に堆積した泥と網目に溜まった泥を除去する作業を行ったので、今月(写真右)は浸透ますの存在が確認でき、本来の役割を果たせていました。

夏の若葉の森は様々な花が咲き、カラフルでした。左上から時計回りに、ヤマユリの花、 ヤブミョウガの花、ツユクサの花、ヒイロタケ(毒キノコ)、ヨウシュヤマゴボウ、ワルナスビの花。 (内堀)

若葉緑地の会 その暑さはほんの序の口だった
7月9日(日)曇り 参加者3名
この日も最少人数での活動となったが、南側の住宅との境界部に丈高く茂った草刈りにチャレンジ。5月にかなり刈ったつもりだったのに、その痕跡さえ見えない繁茂ぶり。
作業を始めるとすぐに汗が噴き出る。この日9時の気温は31℃(府中)。幸い、その後はあまり上昇しなかったものの、十分に暑かった。しかし、中旬以降の猛暑日連続の「危険な暑さ」を思えば、これはほんの序の口だった。
樹木が越境しているので対処してほしいとの連絡が住民から緑と公園課にあったとのことだが、私たちが安全に落とせる大枝はないと判断し樹木には手をつけなかった。

崖線上「青空広場」の南側で、クサギがつぼみを傘状にびっしり付けて、いる。近寄ってよく見ると、先端部がほのかに赤らんで美しい。この季節、森に咲く花が少ないので、貴重だ。開花すると、アゲハチョウがよく訪れている。気の毒な和名は、葉を揉んだりすると感じる臭いに由来。対して、花には芳香があるというが、未経験。

クサギは成長が速い植物。5年ほど前に苗木を頂戴して植えたエゴノキに、クサギの幼木が覆い被さるように生育しているのに気付いたので、クサギを除去。写真下の花壇の向こう側にそのエゴノキがある。花壇は緑地の会の初期メンバーが世話をしていた時期もあったが、近年は筋向いの住宅地の方が「花いっぱい運動」に登録して、面倒をみてくださっている。じつに多彩な園芸植物が入れ代わり立ち代わり登場し、樹林の植生といいコントラストをなしている。

若葉町第3緑地でのナラ枯れ感染はシラカシ9本に増えた。衛藤譲二氏の尽力で、うち6本にカシナガトラップを取り付け、3本は幹にシートを巻いて対処した。フラスは出ているが、幸い葉の枯れは認められない(7月末現在)。(大村)
カニ山の会 この暑さでも昆虫は元気!
7月8日(土)曇り 参加者10名
作業前々日、前日と35℃に迫る強い陽射しの天気だったので、開始を30分繰り上げ昼まで(9:30~12:00)の作業とした。 梅雨前線の南下で天気は下り坂(九州中国地方は災害級の雨)、曇り空で温度はそれ程上がらなかったが湿度が高く、作業を始めると直ぐシャツがぐっしょりになった。
今日の作業場所は東樹林の下段区域。宅地との境界は業者による竹藪伐採などがあり、会としては半年近く手を入れてなかったので中はササや常緑低木が繁茂して暗い樹林になってしまっている。これまで除伐、剪定、刈ったササ等は原則として搬出処分をしてきたが、かなりの労力が必要となる上、森の物は森へ返す(循環)最良の方式をなんとか実現できるよう現場処分方式を試行して行くことにした。
そのための粗朶柵作りは次回以降の作業とすることにし、今日は常緑低木(アオキ、ツゲ、シラカシ…)やヒョロヒョロ伸びたムクやエノキの実生、シュロなどを除伐、大きく成長したツバキやツゲの剪定、伸び過ぎたササの刈り払いなどを行った。

カニ山に入るとすぐにカブトムシの残骸を発見!奥の東樹林脇の道にはいくつもの残骸が連なっている。例年カラスにやられたと思われるものをよく見かけるが、こんなに沢山あるのは珍しい。
作業中にあちこちから「カブトムシがいる!」との声が上がる。草むらで見つけたものを作業の邪魔にならないよう太目の幹に避難させる。




予定通り12時作業を終了し、振り返り(感想話し合いなど)をして12時半ころ散会した。
カシノナガキクイムシについては活動の季節になっているはずだが7/8現在、活動を象徴するフラスが見られない。 但し深大寺元町の「22森」では、7月に入って新穿孔(フラス)を確認、ここ数日で状況が劇的に変化し一気に3000を超えるカシナガを捕獲している。 カニ山においても状況の変化を見極めたい。(S&K)
入間・樹林の会
7月15日(土)曇り 気温30℃ 参加者4人
7月初めに新左エ門坂を挟んで向かいにあるNTT側からの倒木で撤去するまで通行止めとなった。フェンスは壊れたままでけが人がでなかったのが幸いである。


よくみると、昨年設置してくれた水留めがすでに壊れて、ひびも入っている。


嬉しいことにNTT側には、2本のヤマユリが。倒木近くで複数の花をつけ、もう1本は坂上で開花。20年近く前には1丁目樹林地でもヤマユリが咲いていたので、林が明るくなると咲くだろうか。


その後、6月に植え替えをしたセンダン等を確認した。センダン、ヤブラン、ナンテンは元気だったが、挿し木したアジサイのうち2本は大丈夫そうで、新たにシャリンバイとジャヤノヒゲを植えた。斜面に土留め柵を作る必要があるが、1か所にとどまった。

駐車場側では、クサギが花を咲かせていたが、枝が民有地に伸びているので伐採対象となる。

カシナガトラップには、1本の木だけにカシノナガキクイムシがいて、他にも生きたコクワガタが何匹かトラップに落ちていたので取り出した。

坂横に罹患した径の太いコナラが見つかったが、1丁目樹林地ではコナラが希少だけに残念である。(安部)