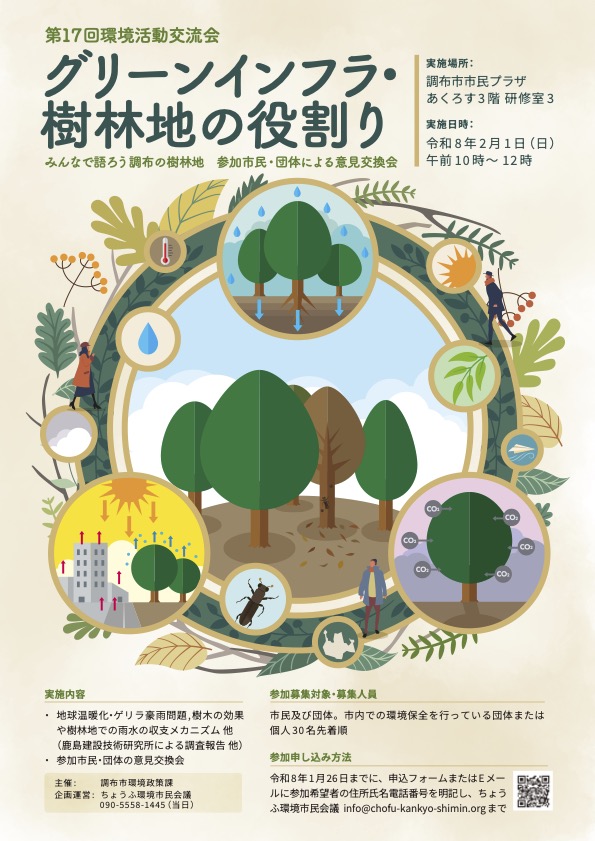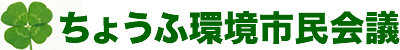カニ山の会 ササ刈り枝下ろし・歓談
11月8日(土)曇/晴 参加者17名
今日はまず東樹林東エリアに山積みしたままになっている剪定枝と枝葉を片付けた。この最終処分も考えなければならない。


まずは片付け
さて本番は東樹林エリア。ここはムクノキ、モチノキ科の実生の成長が早く、幹径5~6㎝の若木がそこらにヒョロヒョロ伸びている。これらが手に余るような成木になる以前に順次処置して行くのが重要だ。
常緑樹のツゲ・ツバキもモチノキ科同様マメに剪定をしないと花期以外は邪魔者になってしまう。

常緑樹の伐採枝がどっさり
春先のモミジイチゴの花は森の大切な彩り、トゲは痛いが刈らない事にしている。ヤブコウジはササと共に刈られそうだが気を付けるしかない。特に注意を要するキンラン、ヤマユリなどはマーキングして刈り取られないようにした。
立ち枯れになった5mほどの樹は「伐るまでも無い、根腐れしているから引き倒せる」との経験者のアドバイスでロープを掛けて数人で引いたところ、見事に根こそぎ倒すことができた。


ロープをかけて根元から倒す
刈ったササは下段域のササ溜めに運び集積した。除伐木、切詰め剪定枝、実生木が想像以上に多く、2カ所に分けて山積みすることになってしまった。
今日は作業後、時間のある人達でベンチのある広場に移動し熱いコーヒーを飲みながら雑木林関連の様々な話ができた。
(S&K)
樹林東エリア センダンの樹の伐採作業
11月15日(土)晴れ 臨時作業参加者13名
時程を考慮し今日の伐倒以前に大枝の切り落としは済ませておいた。センダンの樹高はそれほどではないが最初のロープをかけるところから多少てこずる。日頃は草刈りに精を出している女性や初心者はロープの掛け方、引き方、受け口の入れ方、追い口の入れ方、一つ一つ基本に則り体験しながら慎重に行ったので、幹径30㎝もあるとかなり時間もかかった。それでも他の会のベテランにも声をかけたお陰でなんとか作業が進行。

とうとう倒れた9時過ぎから始まった作業は最後(昼頃)にツルを多めに残し、みんなで引き倒した。幹と大枝を切り分けざっと片付けたが、玉切りの作業が残ってしまった。
(S&K)
崖線ウォークのゴールとして
11月29日(土)晴れ スタッフ参加者12名
崖線ウォークに応募した参加者50名弱がカニ山にゴール。インフルエンザの流行で子供連れのキャンセルが相次いだのは残念だった。
それでも仙川駅前から8㎞ほど頑張って歩いてきた方々は最後にカニ山周辺の地形や歴史的な説明を聞き待望のキャンプ場へ。今回はカマドで焼いたサツモイモの焼け具合も数も十分でスタッフを含め皆満足できたようだ。

崖線ウオーク ゴール