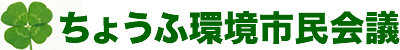若葉緑地の会 スミレがこんなに殖えた
4月12日(日) 晴れ 参加者4名
いつものとおり緑地内と外周道路のゴミ拾いの後、全員で「南広場」のスミレ「保護区」に向かった。
近づくと「わぁッ」と声が上がる。3月の活動日には、小さなつぼみが一、二見られただけだったが、たくさんの花をつけた群落がいくつも広がっている。しかも、昨年まで、特に小形だった白花のマルバスミレがずいぶん大きく育って、タチツボスミレと張り合っているようだ。
3年前、マルバスミレを見つけたのをきっかけに、冬の午後には陽だまりになる林床にスミレの「保護区」を設けた。
昨年秋から、周りのアズマネザサを刈ったり、3月以降は被さっている落葉を少し除けてやるなどの世話をしてきたことが、功を奏したようだ。
この冬は3月初旬までは少雨傾向だったが、中旬から4月上旬にかけて170mmを超える雨が降ったこと(府中)も、良かったのではないだろうか。
これからは、散布される種子が、落葉の上ではなく土に落ちるように、周りの落葉を掃除してやる仕事がある。



例年だと用具倉庫裏の一画がタチツボスミレの花畑になるが、今年は花が少ない。冬の間、キヅタが地面を覆っているのが気になっていた。その影響か。
残念な思いでいると、すぐ近くにチゴユリが咲いていると教えていただいた。下向きに開く「内気な」花。なかなか顔を見せてくれないので、ちょっと仰向けになってもらった。それが2枚目の写真。小さく清楚に整った花だ。


肝心の作業は、「桜広場」の住宅寄りの辺りがブッシュ状になってきたのを伐開。
藪のなかでサンショウの花が咲き始めていたが、この日見たのは雄株だけだった。
作業の終わりに、香りの高い若葉を少し頂戴した。(大村)


若葉3・1会 若葉の森
雨のため作業無し
カニ山の会 問題続々、その対策は?
4月9日(土) 晴れ 参加者11名
午前中は東樹林の整備をすることにして、1~3月の定例活動で積み残しになっていた剪定枝や刈ったササを数人で収集し、リヤカーとフゴでカニ山北口付近の仮置き場に廃棄した。その他、中途半端になっていた上段、下段の落ち葉掻きを行い、新しい落ち葉溜めに入れ少しでもカサを減らすべく踏み込む。
昼までで帰る人が多いため12時前に作業を終わり、皆でふりかえりを行う。「全力でやっても中段の落ち葉掻きまでは出来なかった。体力差に合せた作業計画にして欲しい。落ち葉を掻いていると実生のコナラを沢山見掛ける。育てて森を更新して行けばいい」などの意見が出た。
昼食後残ったメンバーで、東樹林、東樹林東、キャンプ場北の活動区域を見て回りながら、問題点、改善策を話し合う。主に土砂流れ・裸地化・ナラ枯れ対策などについての話が出た。最後にカマド北の作業地を見まわった折、隣接した大木の森が皆伐されている現場に遭遇。事情が分からないのでなんとも言えないが全員あぜんとなる。

宅地に隣接した保全作業は住民の希望も考慮しながらという話し合い。

コナラの実生。ナラ枯れによりコナラ・クヌギなどの実生木は大切にしたい。

春爛漫! 傍らではグミが満開!

カニ山カマド北東にある民有地の森が無くなってしまった。
4月30日(土)臨時作業 晴れ 参加者6名
クリアフォルダー20シートで11組のトラップを作る。
カシナガトラップも沢山に越したことは無いが、清掃、水の交換、捕獲数のカウントとメンテナンスが結構大変。 会の能力から取付け数は5、6カ所程度が適量と考え3年前からの状況も考慮し狭いエリア2か所にコナラを4本ずつ、クヌギはカマドの傍らに1本のみの計9本に取り付け。ちょっと意外だがクヌギはどうも1本しか存在しておらずカニ山の落葉樹はコナラ・シデがほとんどを占めている。(S&K)

トラップ設置のようす
入間・樹林の会
4月17日(日) 参加者9名
雑木林広場でキンランの確認後、ツバキの森でナラ枯れのため伐倒した4本のシラカシを確認した。罹患していたシラカシが大径木だったこともありぽっかり樹冠があき明るくなった。今後の植生の変化をみていくために、5m四方の植生調査を行うことにし、シラカシ・エノキ・ケヤキ・ムクノキの実生とヒサカキの5種を確認した。
ジャガの森ではニリンソウが咲き44種を、雑木林広場では34種を確認した。ウラシマソウは樹林地内でも分布が広がっている。花はキンラン・ウラシマソウ・ニリンソウ・ジュウニヒトエ・キランソウ・シャガ・アオキ・サンショウ・ツバキ・セリバヒエンソウ・キュウリグサ・エナシヒゴグサ・ヤブニンジン・ムラサキケマン・ハルジオン・ハナニラを、実はアオキ・ヤブミョウガを確認した。坂道はシラカシなどの常緑の落葉の掃除を最後に行った。
次回は5月15日(日)保全活動を予定している。 (安部)